こんにちは!仏壇工芸ほりおの岩崎です。
今回も仏壇職人と寺の住職の二つの肩書きの目線から色々な疑問や問題について話していこうかと思います。
さて、今回は仏壇のお道具(仏具)の中でも、なくてはならないもの「三具足」のお話しをします。
ちなみに読み方は「みつぐそく」または「さんぐそく」と読みます。
三具足は「花立て」「香炉(線香立て)」「燭台(ロウソク立て・火立て)」の三つのことを指します。
飾り方は御本尊(仏さま)に向かって左側に花立、真ん中に香炉、右側に燭台を配置するのが一般的です。
宗派によって形、色、は様々で色々なものがありますが基本的な飾り方は上記の通りになります。
ではここからは何故この「三具足」が必要なのか?をお話ししていきます。
そもそも「具足」って何??と思われる人もいるのではないでしょうか?
「具足」という言葉には「過不足がなく、必要なものがそろっている」という意味があり、三具足は仏教用具の中でも特別な位置を占めています。
仏具には一つ一つにしっかりとした飾る意味があります。
それではこの三つの「具足」の意味を簡単にお話ししていきましょう。
1.花立て
花を供えることで、仏の世界の美しさを表現します。
故人の三十五日または四十九日まではなるべくカラフルな色の花は避けた方が良いですが、忌明け以降は鮮やかな色合いの花でも問題ありません。
✅故人の好きだった花を飾ると、良い思い出話もできるかもしれませんね
2.香炉
お香を焚くことで、仏の世界の清浄さを表し、また故人への追悼の気持ちを表します。
またその空間がお香の香りで満たされる事によって、お参りする人の心も浄化し、より清らかな気持ちで仏壇に手を合わせることができます。
✅ご遺体の保存が難しかった昔は、腐敗臭を紛らわすため必要以上にお香を焚いたという話しも、、、、
3.燭台
ロウソクの光は仏の智慧を象徴し、暗闇を照らす導きの光を表します。
また我々の煩悩の闇を明るく照らしてくれるという意味もあります。
✅ロウソクの炎には「1/fゆらぎ」と呼ばれる自然な揺らぎがあり、これは小川のせせらぎや木々が揺れる音と同じリズムです。このリズムは、人に安心感やリラックスをもたらします。仏壇の前で心を落ち着かせるにはピッタリですね!
三具足は宗派によって様々な形、色があります。
近年では多種多様な仏壇も増えてきて、それぞれの仏壇に合わせた仏具があります。
材質も昔ながらの真鍮製のものだけでなく、陶器やガラスのオシャレなものも増えてきました。

でも時代が変わり、見た目がどれだけ変化しても、大事なことは何一つ変わりようがないものですよね。
私たちの店舗では従来の仏具から、最近の時代に合った新しい仏具まで幅広く取り揃えており、また仏具の修理、お磨きなども承っております。
「今ある仏具が汚くなってきたなぁ、、、」
「ちょっとここの部分がガタついて気になるなぁ、、、」
なんて気になる方はお気軽にご相談ください!
最後まで読んでいただき有難うございました。 南無阿弥陀仏
お問い合わせはこちら https://horio.co.jp/
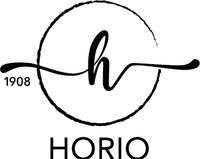
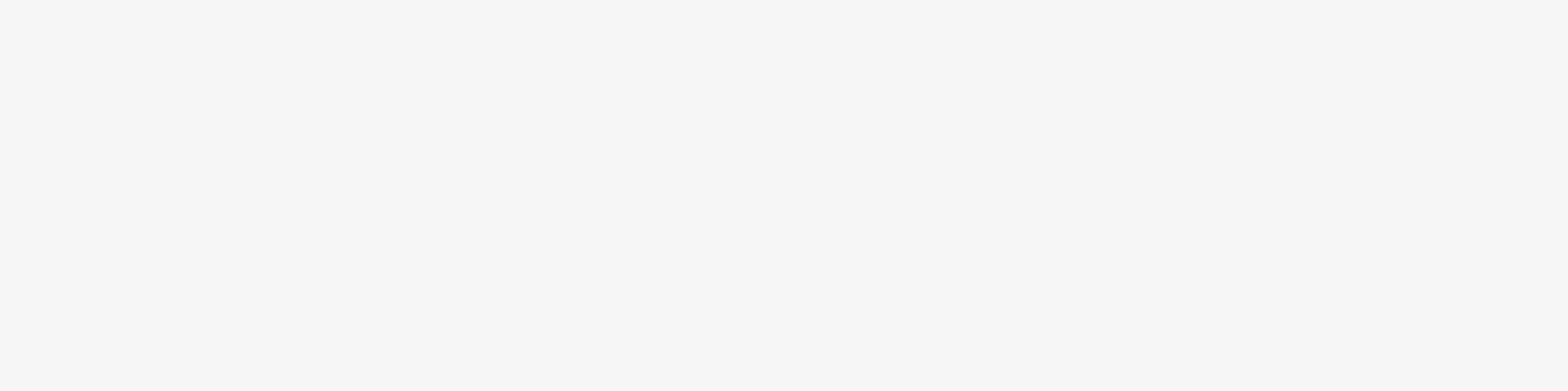
コメントする