こんにちは!仏壇工芸ほりおの岩崎です。
今回も仏壇職人と寺の住職の二つの肩書きの目線から色々な疑問や問題について話していこうかと思います。
さて、今回は皆様にも馴染みが深いと言っても過言ではない「蝋燭(ろうそく)」について少しお話しをしてみたいと思います。
✅蝋燭の歴史はとても古く、古代エジプトから始まり、シルクロードを経て中国、そして7世紀頃に日本に伝来しました。当初は輸入品でしたが、9世紀以降国内生産が始まり、和ろうそくが誕生しました。長らく高価で貴重品でしたが、江戸時代には会津絵蝋燭が特産品として発展し、明治時代には国際的にも認められました。
普段私達が何気なく使っている蝋燭にもこんなに長い歴史があるんですね。
以前にもお話しさせてもらいましたが、蝋燭の炎には心を落ち着かせてくれる効果があります。
蝋燭の炎のゆらめきは「1/fゆらぎ」と呼ばれる特殊なパターンで揺らいでいます。
このゆらぎは規則性と不規則性が調和したリズムを持ち、人間の生体リズムと共振することで心地よさと安らぎをもたらします。
小川のせせらぎや雨の音などの自然現象も同じ効果があるみたいですよ!
お寺や家でお参りをする時には欠かせないものの1つである「蝋燭」
仏教において蝋燭の灯りは仏さまの智慧と慈悲を象徴しています。
この光は無知の闇を照らし、悟りへの道を示すとされています。
また、邪念や煩悩を払い、心を浄める力があるとされています。
日々の目まぐるしい生活に疲れている私たち現代人。
たまにはゆっくりとお仏壇の前に座り、蝋燭に火を灯してボーッとしてみませんか?
「生き急ぎ過ぎでないかい?ちょっと休んでいきなさいよ。」
なんて仏さまの労いの言葉が聴こえてくるかもしれませんよ?😀

ちなみにこれは当社の職人さんが1本1本丁寧に手作業で仕上げた絵ロウソクです。
なんか火をつけるのが勿体なくなりますよね。😊
最後まで読んでいただき有難うございました。 南無阿弥陀仏
お問い合わせはこちら https://horio.co.jp/
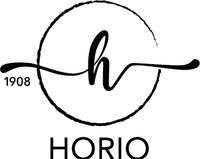
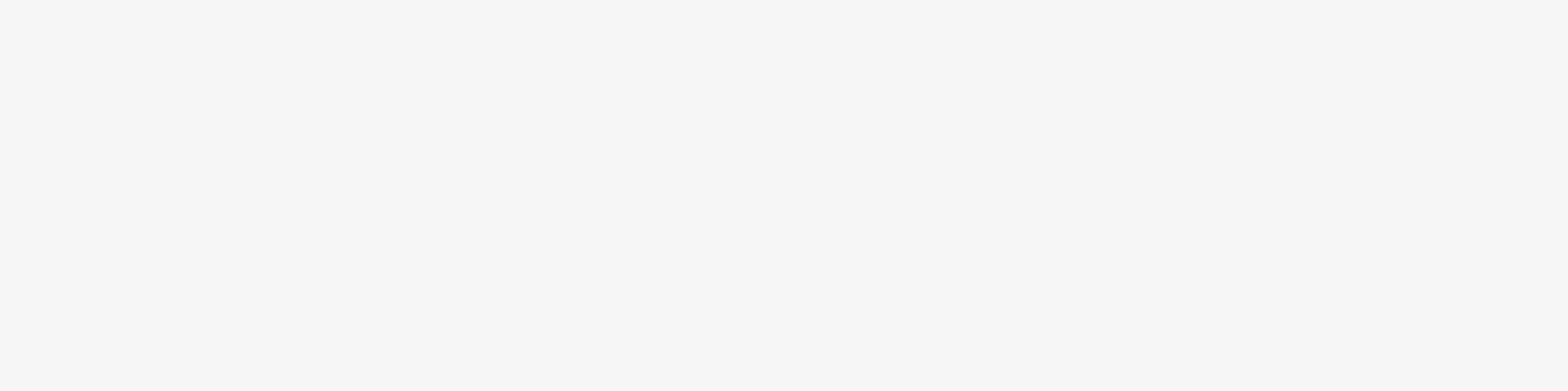
コメントする