
みなさんは「お彼岸」と聞くと、何を思い浮かべますか?
お墓参りや「ぼたもち・おはぎ」をお供えする風景を思い出す方も多いでしょう。
さて今回は、そんな「お彼岸」についてお話しさせてもらいます😊
実はお彼岸は、日本の仏教ならではの行事で、春分・秋分の日を中心に前後3日ずつ、合計7日間を指します。
✅お彼岸の意味
「彼岸」とは、仏教でいう“悟りの世界”のこと。
迷いや苦しみに満ちたこの世を「此岸(しがん)」といい、そこから仏の世界へと渡ることを彼岸と呼びます。
春分・秋分の日は太陽が真東から昇り真西に沈みます。仏教では西方に極楽浄土があるとされ、この時期はご先祖さまを偲び、心を仏に向けやすい特別なときと考えられてきました。
✅お彼岸にすること
お彼岸の期間には、次のような習慣があります。
・お墓参り:墓石を掃除し、感謝の気持ちを伝える
・仏壇での供養:花やお菓子をお供えし、春は「ぼたもち」、秋は「おはぎ」を供える
・心を整える修行:「布施・忍耐・努力」など六波羅蜜の実践を心がける
お彼岸は単なる年中行事ではなく、ご先祖への感謝と、自分の心を磨く時間なのです。
✅日本独特の行事に育った背景
「彼岸」という言葉自体はインドや中国にもありますが、春分・秋分と結びつけて行事化したのは日本独自。
自然の移ろいと仏教の教えを結びつけ、ご先祖を想う習慣へと育んだところに、日本人らしい感性が見えてきます。
お客様と接していると、お彼岸をきっかけに「普段はあまり仏壇に手を合わせないけれど、この時期だけは家族で集まる」という声をよく耳にします。
実はそれで十分なのです。大切なのは、形式よりも「感謝の気持ちを持つこと」。
仏壇をきれいに掃除し、お花を供えたり、好きだったお菓子を置いたりするだけで、ご先祖を偲ぶ立派な供養になります。
お彼岸は「ご先祖さまを想う心」と「自分を見つめ直す心」を大切にする行事です。
忙しい日常の中でも、この時期だけは少し立ち止まり、仏壇やお墓の前で手を合わせてみませんか?
その時間が、家族のつながりや自分自身の心を豊かにしてくれるはずです。
✅オマケの小ネタ
「ぼたもち」と「おはぎ」は同じ食べ物ですが、季節や呼び名で違いがあります。
・春の牡丹餅(ぼたもち):牡丹の花にちなみ、丸く大きめ。こしあんを使うとされる説が有力。
・秋のおはぎ:萩の花にちなみ、小ぶりで収穫したての小豆を粒あんで仕上げることが多い。
ただし、地域や家庭によっては逆に伝わっている場合もあり、「ぼたもち=粒あん」「おはぎ=こしあん」とする説も存在します。
つまり、正解は一つではなく、暮らしや風習に根ざした違いなのです。
最後まで読んでいただき有難うございました 南無阿弥陀仏
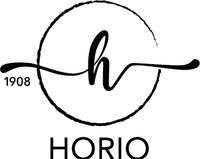
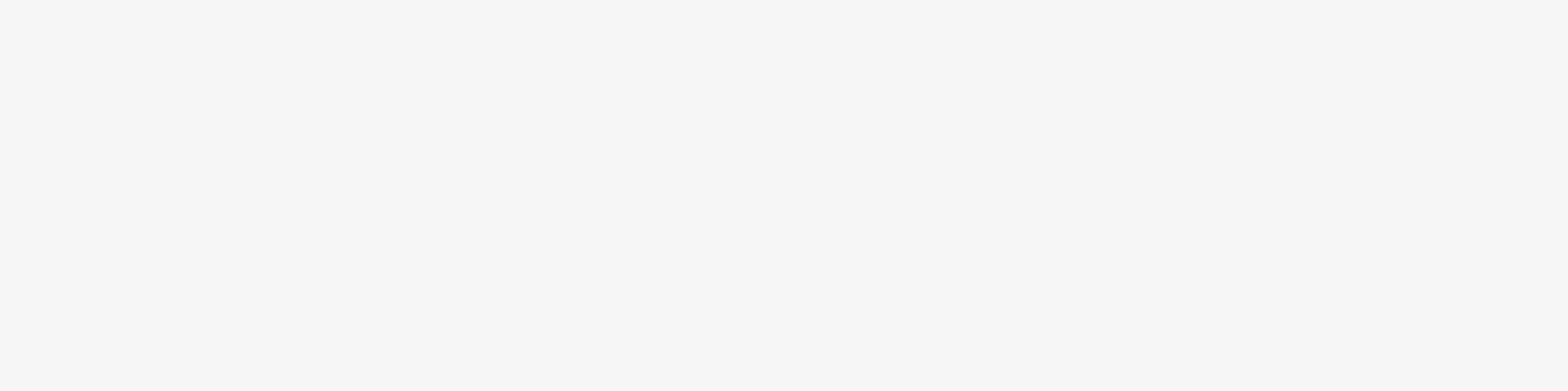
コメントする