
さて今回は「年忌法要の区切りって、どうして決まってるの?」という疑問についてお話しさせてもらおうかと思います。
「どうして一周忌とか三回忌とか、決まった年に法要をするんですか?」
お寺だけでなく、仏壇屋に勤めているとお客様からもよく尋ねられます。
確かに不思議ですよね。三や七や十三といった数字には、実は仏教の教えと日本人の暮らしの知恵が深く関わっているんです。
七日ごとの供養が始まり
もともと仏教がインドで説かれた頃、人は亡くなると七日ごとに次の世界へ進むと考えられていました。
だから七日ごとに供養をして、四十九日で一区切り。これが中国を経て日本に伝わり、今の「四十九日法要」という形になりました。
暦の感覚と仏教の数字
日本人は昔から一年を一区切りに暮らしてきました。その感覚が仏教の供養と重なり、「毎年の命日に故人をしのぼう」という心が育ちました。
そして仏教で大切にされる「三」や「七」といった数字と結びつき、一周忌、三回忌、七回忌、十三回忌…といった年忌法要が生まれたのです。
日本ならではの工夫
さらに日本独自の工夫もあります。
三十三回忌は観音さまの三十三のお姿にちなみ、「ここでご先祖も仏さまのお仲間に入られた」として弔い上げにする地域もあります。
五十回忌は、家や地域が覚えていられる限界を表すとも言われています。
仏壇と年忌法要
年忌法要の時期になると「お仏壇をきれいに整えたい」「お位牌を新しく作りたい」というご相談をよくいただきます。
年忌法要は単に「決まりだからする」のではなく、ご先祖に感謝の思いをあらわす大切な節目。その心を形にあらわす場所こそが、お仏壇なんですね。
まとめ
年忌法要の数字は、ただの決まりではなく、仏さまの教えと日本人の暮らしの知恵が重なったものです。
そして、そのご縁を日々つないでくれるのがお仏壇です。
ご先祖を偲ぶたびに仏壇の前に手を合わせる。その積み重ねが、私たちの暮らしをやさしく支えてくれているのだと思います。
もし年忌を前にして「お仏壇を整えたいな」と思われたら、どうぞお気軽にご相談ください。
ご先祖を大切にするお気持ちを、いちばん良い形でお手伝いさせていただきます。
最後まで読んでいただきありがとうございました😊 南無阿弥陀仏
お問い合わせはこちら https://horio.co.jp/
お仏壇のお洗濯はこちら https://horio.co.jp/pages/repair
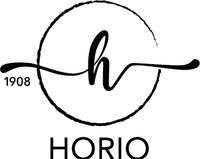
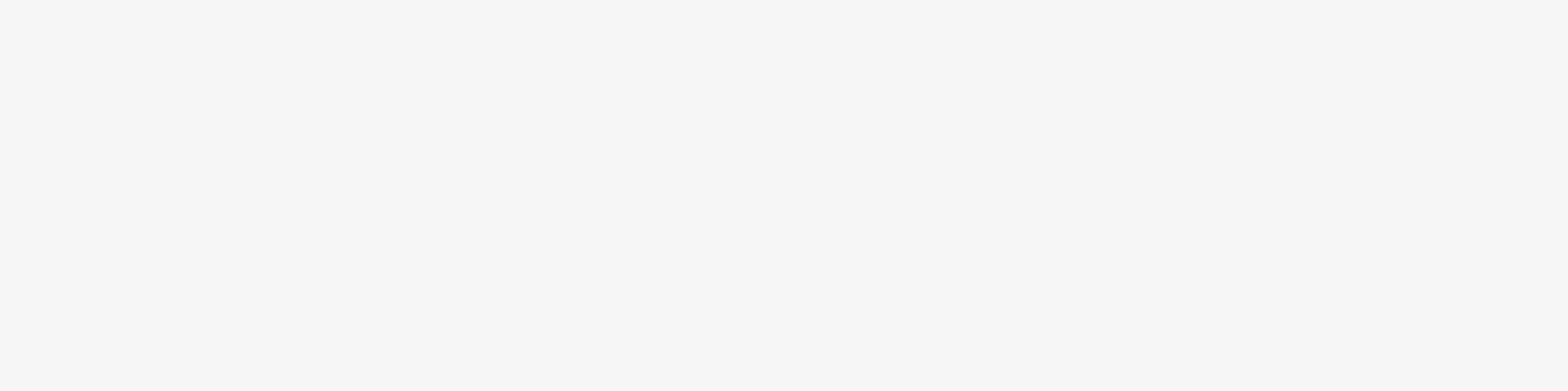
コメントする