こんにちは!仏壇工芸ほりおの岩崎です。
今回も仏壇職人と寺の住職の二つの肩書きの目線から色々な疑問や問題について話していこうかと思います。
さて今回は雑談になります。お付き合いいただければ幸いです😊
皆さんは今現在、お寺というものをどうとらえていますか?
私は寺の生まれですので、物心ついた時からなんとなく自然にただそこにあるもの、みたいな感覚で過ごしてきましたが、やはりそうじゃない人からしてみれば「馴染みのないものなのでしょうね。(事実、子供の頃は寺の子というだけで珍しがられたものです、、、。)
大人になるにつれ、その「馴染みのない」という気持ちはより顕著になっていき、そして「近寄りがたい」になり、最後は「今は自分には関係のない」という事になってしまうのでしょうね。(仏教がなんとなく「死」というものを連想するイメージがあるので、そこが敬遠されがちなところもあるのは否めませんけど、、、)
その反面、子供の行動というものは見ていてこちらも気付かされる事が多いです。
私の住んでいる地域では年に1回、子供会と題して地域の子供に集まってもらい、お寺で色々なレクリエーションをする行事を行っています。
子供は親御さんと一緒に来るわけなのですが、本堂に入るやいなや親御さんそっちのけで、まず本尊に向かい正座して合掌するんですよ。
しかし、いざレクリエーションが始まると水を得た魚のように本堂や境内を全力で走り回るんですね。
「静」と「動」がハッキリしてると言うか、なんと言うか、、、😅
親御さんや我々住職は目を丸くして、ただただ唖然としてます(笑)
しかし、そもそもお寺という場所はこうゆうものなのでは、と思います。
近年では儀式を行う神聖で硬いイメージがどうしても定着していますが、本来は人々が自然に集まり、仏さまの前で地域の交流が生まれる、そんな気軽な場所であったと言います。
私も子供の頃は近所のお寺がちょっとした遊園地のような感覚で、待ち合わせたわけでもなく近所の子供達が自然に集まり、鬼ごっこや隠れんぼをして遊んだ記憶があります。
たまには何も考えず、フラッと昔のように戻れたらな〜、っと感じつつ毎日の慌ただしさに流されている日々でございます😅
仏壇工芸ほりおも、そんな自然な地域の交流の場になれたらと日々精進しております😊
最後まで読んでいただき有難うございます 南無阿弥陀仏
お問い合わせはこちら https://horio.co.jp/
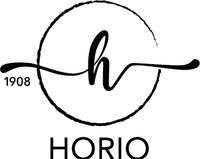
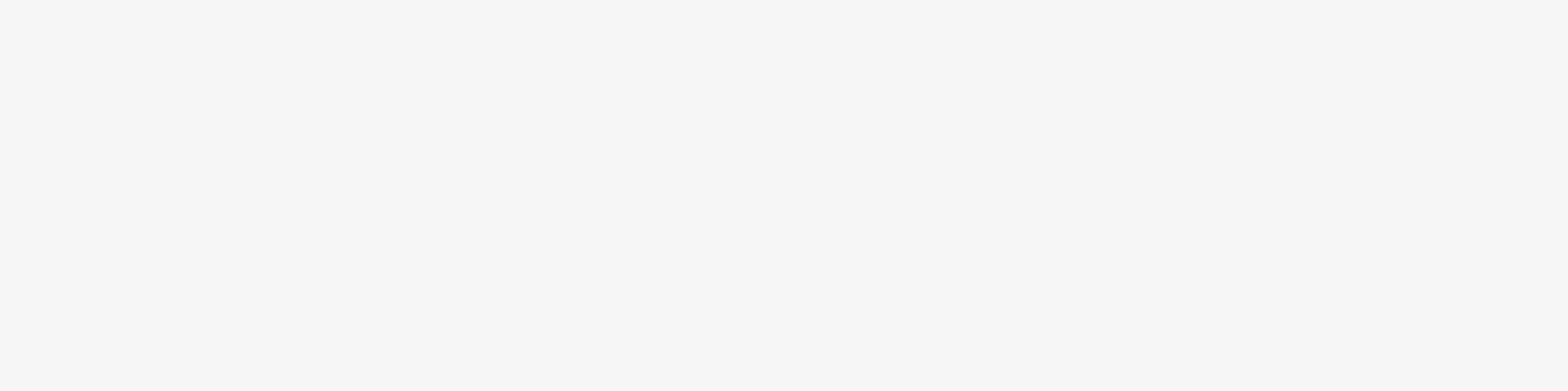
コメントする