
「喪中なので…」「まだ忌中で…」
お葬式のあと、こんな言葉を耳にすることがありますよね。
でも実際には、「喪中」と「忌中」の違いがあいまいなままになっている方も多いのではないでしょうか。
今回は、仏教の考えと、仏壇屋の暮らしの知恵、両方の立場から簡単にお話しします。
✅ 忌中(きちゅう)とは?
忌中は、亡くなった日から四十九日までの期間のことです。
仏教では、この間に故人の魂があの世へ旅立つ準備をしていると考えられています。
この時期は「慎みの期間」とされ
・神社へのお参りを控える
・結婚式やお祝いごとへの出席を控える
・静かに故人を偲ぶ
といった過ごし方をします。
四十九日を過ぎると「忌明け」となり、宗教的な制限はなくなります。
✅ 喪中(もちゅう)とは?
喪中は、亡くなった日からおよそ1年間、
故人を思いながら静かに過ごす期間をいいます。
忌中が宗教的な意味を持つのに対して、
喪中は生活の中での心の整理期間のようなものです。
・年賀状を出さず、喪中はがきでお知らせする
・新年のお祝いを控える
・派手な集まりや宴席を避ける
このような形で気持ちを整えていきます。
✅ 忌明けしたらお祝い事はしてもいいの?
これはよくある質問なのですが、
四十九日の忌明け後は問題ありません。
宗教的には、故人の魂が安らかに旅立たれた区切りです。
ただし、喪中の一年間は「故人を偲ぶ時間」でもありますので・・
・自分が主催する結婚式やお祝いごとは少し時期をずらす
・他の方のお祝いに招かれたときは、控えめな装い・言葉づかいで参加する
といった心配りを大切にしたいところです。
忌明けは“形の区切り”、喪中は“心の整理”の時間だと私は思います🙂
✅ 忌中・喪中はどの家族まで関係するの?
現代の目安としては、二親等以内の家族が対象になります。
(配偶者・父母・子・兄弟姉妹・祖父母・孫まで)
| 続柄 | 喪中・忌中の対象 | 喪中の目安期間 |
|---|---|---|
| 配偶者 | 〇(最も深い喪) | 約1年 |
| 父母 | 〇 | 約1年 |
| 子ども | 〇 | 約1年 |
| 兄弟姉妹 | 〇 | 約3〜6か月 |
| 祖父母 | 〇(同居・親交の深さによる) | 約6か月 |
| 孫 | △(関係の深さによる) | 約3〜6か月 |
| おじ・おば・いとこ | ✕(原則対象外) | — |
仏壇屋としての実感では、同じ家で暮らしていたかどうかが一つの目安です。
同居していた祖父母などは、自然に喪中として静かに過ごされる方が多いです。
人が亡くなったあとの時間は、
悲しみの中にも“感謝”や“つながり”を感じる大切なときです。
無理をせず、静かに、心を込めて過ごしましょう。
それがいちばんの供養になると思いますよ😊
ご進物などのお問い合わせはコチラ https://horio.co.jp/collections
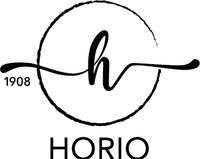
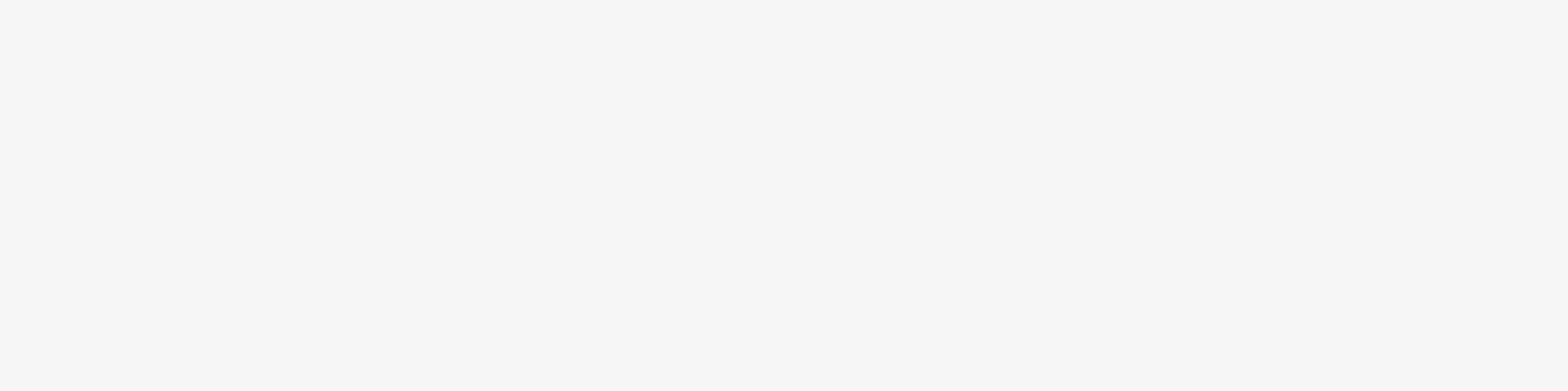
コメントする