
子供の頃よく亡くなった祖母に「そんな悪さばっかりしとるといつかバチが当たるよ!」と言われたものです、、、、、😅
皆様にも多少なりとも心当たりがあるのではないでしょうか?
しかし、「バチってなんやねん」と子供心に思ったのもあります。
空から自分の頭に何かが降ってくるわけでもなく、目に見えて何か不幸が訪れるわけでもなく、、、、(親父の拳骨はもれなく飛んできましたが、、、、)
その頃の私には祖母が何を伝えたかったのかも分からず、ただただお叱りの言葉としてビビっていたものです。
大人になり、社会に出て、色々な経験を重ね、ふと祖母を思い出し、あの時何を伝えたかったのだろうと、、、、
「因果応報」
これを伝えたかったのでないか?と改めて考えさせられます🤔
さて今回は、私たちが日常で耳にする「因果応報」という言葉。どこか堅苦しく感じるかもしれませんが、実は私たちの暮らしと深くつながっています。ここでは住職と仏壇屋の二つの立場から、その意味と大切さをお話ししようかとおもいます。
「因果応報」とは、行いには必ず結果があり、その結果に応じた報いがあるという仏教の教えです。
良い行いは良い果報を、悪い行いは悪い果報を生みます。しかし、それがすぐに現れるとは限りません。仏教では次のように整理されています。
✅ 現報:すぐに報いがある(例:嘘をついたらすぐに信用を失う)
✅ 生報:この人生のうちに返ってくる(例:人を助けたことで後に自分も助けられる)
✅ 後報:来世に現れる
✅ 無定報:いつ現れるか定まらないが、必ず報いはある
これは「善いことをすれば安心して生きられる」と同時に「悪いことも必ず自分に返る」という戒めにもなります。つまり、日々の行動に責任を持つことが大切だと説いているのです。
「そんな単純なものじゃないやろ?」と思われるかもですが、やはり良い事をすれば気持ちは良いものですし、悪い事をすれば気持ちは晴れませんし、見返りを求めるのではなく、自身が心穏やかに生ていくための指針みたいなものかもしれませんね。
仏壇屋としてお客様と接していると、この「因果応報」を生活の中で実感する瞬間が多くあります。
たとえば、ご先祖さまを大切にし、毎日お仏壇に手を合わせているご家庭では、家族の絆が深まり、穏やかな空気に包まれているのを感じます。これこそが「善因善果」の姿でしょう。
また、お仏壇を前に「ありがとう」と感謝を伝えることも、因果応報の実践ではないでしょうか。
感謝の心は不思議と自分の心を満たし、やがて周囲の人間関係も円滑にしてくれます。小さな習慣が、未来の大きな果報につながっていくと思います。
簡単ではありますがまとめますと、住職の立場からは「因果応報」は仏教の根本的な真理であり、人を正しい道へ導く教え。
仏壇屋の立場からは、それが日常の習慣や家族の暮らしの中に息づいていることを実感できます。
善い因を積むことは、未来の自分や家族を豊かにする第一歩。
今日から「ありがとう」と感謝を重ねることこそ、因果応報の実践ではないでしょうか?
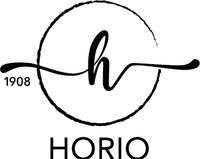
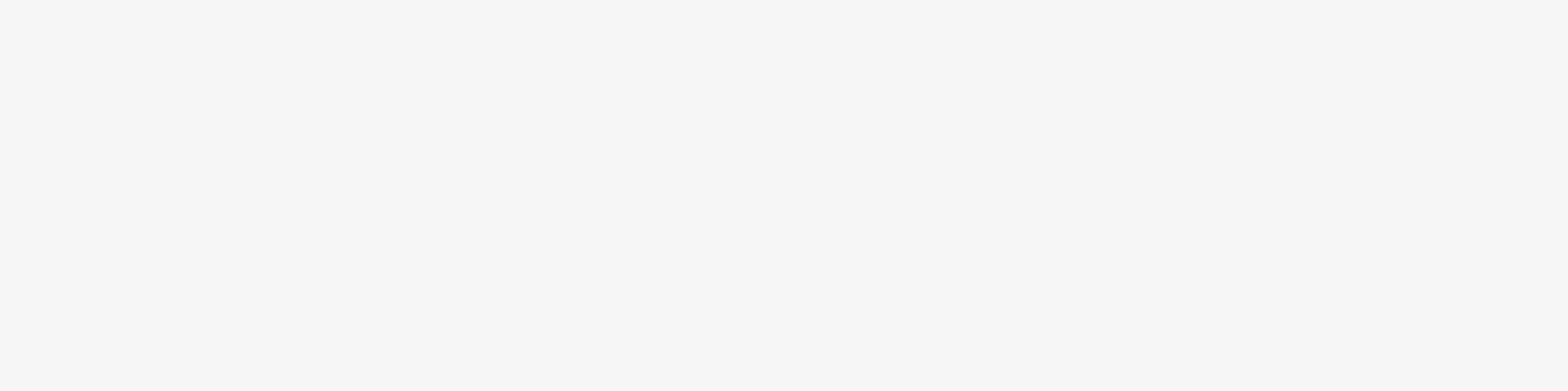
コメントする